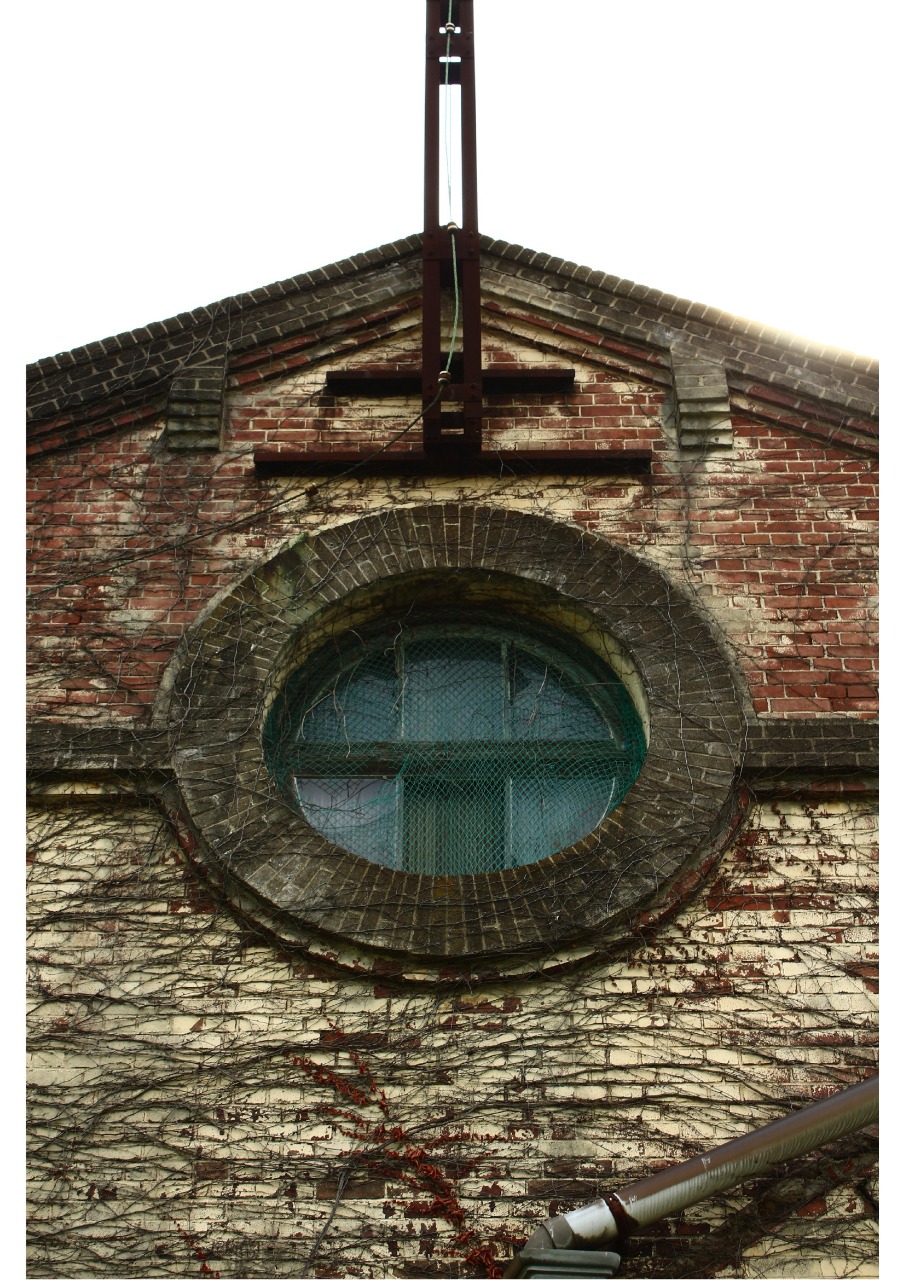「なつかしの香月線」展
日本初の鉄道開通から筑豊の鉄道まで
明治時代に入り、日本が産業を興し近代的に発展していくためには鉄道が必要であるという機運が高まり、明治5(1872)年、新橋から横浜間にわが国最初の鉄道が開通しました。この鉄道敷設の機運は九州にも広がり、明治16(1883)年には九州の鉄道建設の計画が具体化し始めました。
その後、明治21(1888)年6月に民営の九州鉄道会社が設立され、明治22(1889)年12月、博多から千歳川(現在の筑後川)間に九州で初めて鉄道が敷設されました。
北九州地域には、明治24(1891)年2月に黒崎から遠賀川間が開通し、同年4月には門司港まで延長され、これによって九州鉄道門司から高瀬間が開通しました。
時を同じくして、筑豊地域でも鉄道が開通しました。明治24(1891)年8月30日、筑豊興業鉄道会社によって若松から直方間が敷設されたのです。
この頃、筑豊地域はようやく石炭の産出が増え始め、これまで遠賀川や堀川の水運に頼っていた石炭輸送は限界を迎えていました。そこで、明治21(1888)年6月に貝島、安川、麻生など筑豊五郡の炭坑主などが筑豊興業鉄道会社を設立し、石炭運搬を目的とした鉄道敷設を出願、完成させました。
日本初の鉄道開通から筑豊の鉄道まで
明治時代に入り、日本が産業を興し近代的に発展していくためには鉄道が必要であるという機運が高まり、明治5(1872)年、新橋から横浜間にわが国最初の鉄道が開通しました。この鉄道敷設の機運は九州にも広がり、明治16(1883)年には九州の鉄道建設の計画が具体化し始めました。
その後、明治21(1888)年6月に民営の九州鉄道会社が設立され、明治22(1889)年12月、博多から千歳川(現在の筑後川)間に九州で初めて鉄道が敷設されました。
北九州地域には、明治24(1891)年2月に黒崎から遠賀川間が開通し、同年4月には門司港まで延長され、これによって九州鉄道門司から高瀬間が開通しました。
時を同じくして、筑豊地域でも鉄道が開通しました。明治24(1891)年8月30日、筑豊興業鉄道会社によって若松から直方間が敷設されたのです。
この頃、筑豊地域はようやく石炭の産出が増え始め、これまで遠賀川や堀川の水運に頼っていた石炭輸送は限界を迎えていました。そこで、明治21(1888)年6月に貝島、安川、麻生など筑豊五郡の炭坑主などが筑豊興業鉄道会社を設立し、石炭運搬を目的とした鉄道敷設を出願、完成させました。
日本初の鉄道開通から筑豊の鉄道まで
明治時代に入り、日本が産業を興し近代的に発展していくためには鉄道が必要であるという機運が高まり、明治5(1872)年、新橋から横浜間にわが国最初の鉄道が開通しました。この鉄道敷設の機運は九州にも広がり、明治16(1883)年には九州の鉄道建設の計画が具体化し始めました。
その後、明治21(1888)年6月に民営の九州鉄道会社が設立され、明治22(1889)年12月、博多から千歳川(現在の筑後川)間に九州で初めて鉄道が敷設されました。
北九州地域には、明治24(1891)年2月に黒崎から遠賀川間が開通し、同年4月には門司港まで延長され、これによって九州鉄道門司から高瀬間が開通しました。
時を同じくして、筑豊地域でも鉄道が開通しました。明治24(1891)年8月30日、筑豊興業鉄道会社によって若松から直方間が敷設されたのです。
この頃、筑豊地域はようやく石炭の産出が増え始め、これまで遠賀川や堀川の水運に頼っていた石炭輸送は限界を迎えていました。そこで、明治21(1888)年6月に貝島、安川、麻生など筑豊五郡の炭坑主などが筑豊興業鉄道会社を設立し、石炭運搬を目的とした鉄道敷設を出願、完成させました。
日本初の鉄道開通から筑豊の鉄道まで
明治時代に入り、日本が産業を興し近代的に発展していくためには鉄道が必要であるという機運が高まり、明治5(1872)年、新橋から横浜間にわが国最初の鉄道が開通しました。この鉄道敷設の機運は九州にも広がり、明治16(1883)年には九州の鉄道建設の計画が具体化し始めました。
その後、明治21(1888)年6月に民営の九州鉄道会社が設立され、明治22(1889)年12月、博多から千歳川(現在の筑後川)間に九州で初めて鉄道が敷設されました。
北九州地域には、明治24(1891)年2月に黒崎から遠賀川間が開通し、同年4月には門司港まで延長され、これによって九州鉄道門司から高瀬間が開通しました。
時を同じくして、筑豊地域でも鉄道が開通しました。明治24(1891)年8月30日、筑豊興業鉄道会社によって若松から直方間が敷設されたのです。
この頃、筑豊地域はようやく石炭の産出が増え始め、これまで遠賀川や堀川の水運に頼っていた石炭輸送は限界を迎えていました。そこで、明治21(1888)年6月に貝島、安川、麻生など筑豊五郡の炭坑主などが筑豊興業鉄道会社を設立し、石炭運搬を目的とした鉄道敷設を出願、完成させました。
日本初の鉄道開通から筑豊の鉄道まで
明治時代に入り、日本が産業を興し近代的に発展していくためには鉄道が必要であるという機運が高まり、明治5(1872)年、新橋から横浜間にわが国最初の鉄道が開通しました。この鉄道敷設の機運は九州にも広がり、明治16(1883)年には九州の鉄道建設の計画が具体化し始めました。
その後、明治21(1888)年6月に民営の九州鉄道会社が設立され、明治22(1889)年12月、博多から千歳川(現在の筑後川)間に九州で初めて鉄道が敷設されました。
北九州地域には、明治24(1891)年2月に黒崎から遠賀川間が開通し、同年4月には門司港まで延長され、これによって九州鉄道門司から高瀬間が開通しました。
時を同じくして、筑豊地域でも鉄道が開通しました。明治24(1891)年8月30日、筑豊興業鉄道会社によって若松から直方間が敷設されたのです。
この頃、筑豊地域はようやく石炭の産出が増え始め、これまで遠賀川や堀川の水運に頼っていた石炭輸送は限界を迎えていました。そこで、明治21(1888)年6月に貝島、安川、麻生など筑豊五郡の炭坑主などが筑豊興業鉄道会社を設立し、石炭運搬を目的とした鉄道敷設を出願、完成させました。